遺言書の効力で何ができる?できないことや効力を失うケースも解説

法律で定められたルールに則って作成された遺言書には、法的な効力が発生します。
しかし、記載した内容すべてに効力がおよぶわけではなく、効力が発揮される範囲についても法律によって定められています。
本記事では、遺言書の効力によってできることやできないこと、遺言書の効力が失われるケースなどについて解説します。
不公平な遺言書が見つかり内容に疑問を持っている方や、これから遺言書を作成しようとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
-
- 遺言書の効力によってできること・できないこと
- 遺言書が効力を失うケース
- 遺言書の効力が発揮される期間
- 目次
遺言書の効力によってできること
遺言書の効力によってできることは、実は法律で定められており、「法定遺言事項」といいます。
法定遺言事項は全部で10種類以上ありますが、ここでは主な事項について、以下で解説していきます。
相続人と相続割合の指定
遺言書によって、誰がどのような割合で財産を相続するかを指定することができます。
つまり、本人の希望次第では、法定相続人以外の者を受遺者(遺言によって財産を受け取る人)に指定することもできるわけです。
そのため、たとえば、内縁の妻や、孫、義理の娘などに財産を受け継がせるといったことも可能になります。また、特定の人の取り分を多くすることも可能ですので、子どもたちのうち、長男に財産を集中して相続させるといったこともできます。
特定の相続人の廃除
遺言書を残す方に対して、虐待や重大な侮辱などを行った人については、家庭裁判所の判断によってその人の相続権を奪うことができ、これを廃除といいます。
そして遺言書では、特定の相続人を廃除する旨を記載することができます。
廃除についての記載があれば、遺言書を残した方の死後、遺言執行者が家庭裁判所に対象者の廃除を請求します。その後、家庭裁判所が相続権を奪うかどうかを判断し、廃除が認められたら、対象者は相続権を失うことになります。
遺産の分割方法の指定
遺言書では、たとえば「不動産はこのように分けなさい」、「長男には土地を、次男には預金を相続させる」といったように、遺産の分割方法を指定することもできます。
また、相続開始から一定の期間(最長5年)を定めて遺産分割を禁止することもできます。
というのも、相続人のなかに未成年者がいる場合や、一定の冷却期間を設けて冷静な話合いができるようにしたい場合などもあるため、あえて遺産分割を禁止するケースがあるのです。
ただし、相続税申告は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」という期間が設けられており、遺言により遺産分割が禁止されている場合でも期間は延長されません。
相続税の申告期限内に遺産分割ができない場合は、法定相続分どおりに遺産分割をしたと仮定して仮の申告を行い、遺産分割完了後に改めて修正の申告を行う必要があります。
また、相続登記についても、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」という期間が設けられており、遺産分割が禁止されていても期間は延長されません。
この場合は、「相続人申告登記」といって、取り急ぎ、自分が法定相続人であることを申告する手続を行い、遺産分割完了後に改めて相続登記を行う必要があります。
このように手続が複雑な場合は弁護士などに相談をして進めることをおすすめします。
後見人の指定
自分が亡くなって未成年者だけが残されてしまうような場合、遺言書によって未成年者などの後見人になる方を指定しておくことができます。
未成年後見人を指定しておくことで、未成年者が成人するまでの財産の管理をはじめ、監護や教育などを任せることができます。
その分、未成年後見人に対してある程度の責任や権限を持たせることにもなるため、未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」も併せて指定しておくのがよいでしょう。
その他
その他にも、以下のように遺言書の効力によってできることがあります。
| 生命保険金の受取人の変更 | 保険法上、遺言書で受取人を変更することが認められています。 どの保険契約の受取人を変更するのかがわかるよう、保険会社名・保険証券の番号などをきちんと遺言書に記載しましょう。 |
| 遺産の寄付 | 遺言書によって、遺産を慈善団体などの第三者に寄付することもできます。 寄付先の団体などの正式名称などを事前に確認しておきましょう。 |
| 子どもの認知 | 認知とは、婚姻関係にない男女の間で生まれた子どもを自分の子どもとして認めることです。 認知を行うことにより、その子どもは遺言を残した方の法定相続人になります。 |
| 遺言執行者の指定 | 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する手続を担う人のことです。 遺言執行者を指定しておくことで、遺言書の内容どおりの相続が実現しやすくなります。 |
遺言書の効力によってもできないこと
以下に挙げるような事柄は、法定遺言事項には含まれていません。したがって、遺言書の効力によっても実現することができません。
| 養子縁組・離婚・結婚に関する指定 | 遺言書の効力によってできるのは、先ほどご説明した「認知」のみです。 |
| 臓器提供などの指定 | 臓器提供や検体など遺体の扱いについての希望を遺言書に記載すること自体は可能ですが、法的な効力はありません。あくまで付言事項(自身の思いなどを記載したもの)という扱いになります。 |
| 葬儀方法の指定 | 葬儀をどのように行ってほしいかについても、あくまで付言事項であり、残された人たちに強制できるものではありません。 |
| 残された家族への指示・要望 | 残された家族に対するお願いなどを付言事項として記載することはできますが、上記と同様、法的な効力が生じるものではありません。 |
遺言書が効力を失うケース
ご説明したように、法定遺言事項に含まれる内容については、遺言書の効力がおよびます。
しかし、場合によっては遺言書が効力を失うケースがあり、遺言書に書いた内容が実行されないという事態も起こり得ます。
以下で詳しく見ていきましょう。
書き方のルールが守られていない
遺言書の書き方には、法律によって定められた正式なルールがあります。そして、そのルールを守っていないと遺言書が無効になってしまうおそれがあるのです。
というのも、遺言書はその記載内容によって財産の分け方が決まってしまうなど、相続人らに大きな影響をもたらします。そのため、有効な遺言書だといえるには所定のルールをしっかり守ったものである必要があるのです。
なお、書き方のルールについては「遺言書の効力が発揮される書き方のポイント」で触れています。
遺言能力がない被相続人により作成された
遺言書は、遺言能力がない被相続人に作成されても効力を持ちません。「遺言能力」とは、自分が作成した遺言の内容を理解し、遺言によってどのような結果がもたらされるのかを認識できる能力のことです。
そのため、たとえば認知症などで正常な判断ができず、遺言能力がない方によって作成された遺言書は無効となってしまいます。
資格のない証人を依頼した
遺言書のなかでも、特に公正証書遺言を作成する場合は、2人以上の証人の立会いが必要になります。そして、証人になることのできない人が法律によって定められています。
【証人になる資格がない人】
- 未成年者
- 相続人になる可能性がある人・遺言によって財産を受けることになる人、これらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
上記の「証人になる資格がない人」を証人にして作成した公正証書遺言書は無効になります。
実は効力を失わないケース
以下の2つのケースについては、「遺言書が効力を失ってしまう」と思われている人が多いのではないでしょうか。
- 勝手に遺言書を開けた
- 遺留分を侵害していた
しかし、実はこれらは遺言書の効力に影響はありません。
以下で詳しく見ていきましょう。
勝手に遺言書を開けた
公正証書遺言以外の遺言書は、原則として、開ける前に家庭裁判所での検認手続(遺言書の偽造などを防止するための手続)が必要です。この検認手続を経ることなく勝手に遺言書を開けてしまうと5万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、遺言書を開けてしまったからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
万が一、勝手に遺言書を開けてしまったとしても、必ず検認手続を行いましょう。
遺留分を侵害していた
たとえば、特定の者にだけ遺産を相続させるような内容の遺言書を作成した場合、ほかの相続人の遺留分を侵害することがあります。「遺留分」とは、相続人に保障された最低限の取り分のことですが、たとえ遺留分の侵害があったとしても、遺言書自体が無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を侵害した場合、ほかの相続人によって遺留分侵害額の請求が行われ、金銭的な解決が図られることになります。
- 遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料 -

-
電話で無料相談する
朝9時~夜10時・土日祝日も受付中
Webで
相談申込み 24時間受付
遺言書の効力が発揮される期間
遺言書には、特に有効期限があるわけではありません。そのため、何十年も前の遺言書だからといって効力がなくなるわけではないのです。
また、遺言書の効力は、遺言書を残した方が亡くなった時点から発生します。
ただし、遺言の内容を変えるために遺言書をあとから新しく作り直したような場合は、前の遺言書は撤回されたものとみなされ、あとに作った遺言書が優先されることになります。
遺言書の効力が発揮される書き方のポイント
先ほどもご説明したように、遺言書の効力がきちんと発揮されるには、民法で定められたルールをしっかり守ったうえで作成する必要があります。
遺言書のなかで、もっとも手軽に作成できるのが自筆証書遺言ですが、その作成特に注意すべきポイントが以下の4つです。
- すべての文章を手書きで書くこと
- 作成した日付も手書きで明記すること
- 署名・押印をすること
- 訂正のルールを守ること
遺言書の書き方のポイントやルールについて、もっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
遺言書でお困りならアディーレへ
遺言書は、残されたご家族のために、ご自身の意思や希望を伝えたり、トラブルにならないようにしたりするために作成するものです。
そのため、法律によってさまざまな効力を保証されていますが、詳しい知識と理解がなければ、その効力をうまく活用できずに、ご自身の思いが果たされないおそれもあります
アディーレでは、遺言書作成のご相談やご依頼を積極的に承っております。
アディーレなら、遺言書作成に関するご相談は何度でも無料ですので、遺言書作成に少しでもご不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部


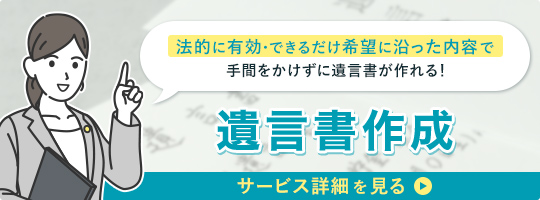


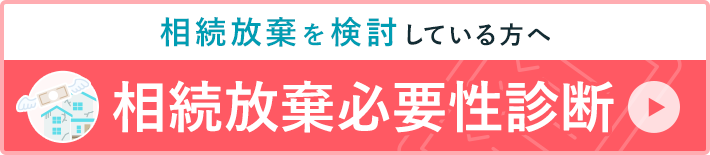

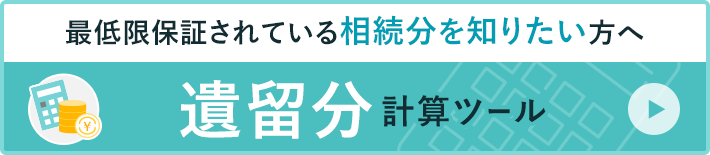



弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。